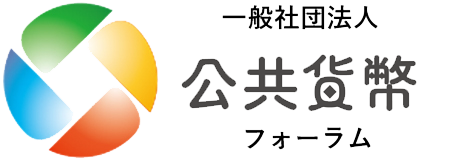公共貨幣システムへ移行する具体的な道筋を示すため、「日本国公共貨幣法」の試案を作成いたしました。これは、現行の「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」及び「日本銀行法」を廃止して、その代わりに制定するものです。
立場の異なる有識者を含めて構成される「公共貨幣委員会」を設置し、公開の場で、貨幣の必要量や新規発行量等を議論することとします。さらに、議論のベースとなるマクロ経済モデルのシミュレーションを国民が検証できるようにすることで、公共貨幣量がオープンな場で合理的に決定されるしくみを組み込んでおります。
日本国公共貨幣法
目的 日本国民の富の源泉は、持続可能な生産活動と、そこから産出される財およびサービスのよどみない流通・交換であり、こうした経済活動を支えるに十分な公共貨幣の供給とその円滑な循環である。しかるに、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(昭和六十二年六月一日法律第四十二号)及び、日本銀行法(平成九年六月十八日法律第八十九号)に立脚する現行の貨幣制度は、こうした日本国民の富をもたらすべき貨幣の役割や機能を十分に発揮させられずにいる。よって本法案はこれら二法を統廃合し、国民をより豊かにする公共貨幣制度を新たに制定することを目的とする。 第一章 貨幣の発行と管理 第一条 貨幣の発行の権能は国会に属する。 二 発行された貨幣は公共貨幣と称し、法貨とする。 第二条 公共貨幣の製造、発行及び管理、運営のために新たに公共貨幣省を設立する。 二 公共貨幣の製造は、現行の造幣局と国立印刷局の紙幣製造部門が合体した公共造幣局が実施し、公共貨幣の製造代金は、貨幣の製造原価等を勘案して算定し公共貨幣省が支払う。 三 発行された公共貨幣は、政府の純資産として計上する。 第二章 公共貨幣の単位、種類、素材及び引換え 第三条 公共貨幣の額面の単位は円とし、その額面価格は一円の整数倍とする。一円未満の金額の計算単位は、銭とし、円の百分の一とする。 二 公共貨幣は十種類とし、一円、五円、十円、五十円、百円、五百円の六種類は日本国硬貨とし、千円、三千円、五千円、一万円の四種類は、日本国紙幣とする。 三 支払うべき金額が一円未満の場合には、全額を切り捨てて計算する。 第四条 公共貨幣の素材、品位、量目及び形式は、公共貨幣委員会で定める。 二 公共貨幣は、デジタル貨幣で代用できる。 第五条 磨損その他の事由により流通に不適当となった公共貨幣は、額面価格で手数料を徴収することなく、引き替えるものとする。 二 公共貨幣の模様の認識が困難なもの又は著しく量目が減少したものは、無効とする。 第三章 公共貨幣大臣及び副大臣 第六条 公共貨幣大臣は、国会が承認・任命し、任期は五年とする。再任の任期は三年とするが、再々任はない。 二 公共貨幣副大臣は二名とし、内閣総理大臣が任命し、任期は公共貨幣大臣に準ずる。 第七条 公共貨幣大臣は、公共貨幣省の長として公共貨幣の製造、発行および管理、運営を統括する。 二 公共貨幣大臣は、公共貨幣に関する情報を全て公開する。 三 公共貨幣副大臣二名は、公共貨幣の供給と需要サイドをそれぞれ担当・統括する。 第八条 公共貨幣大臣は、物価の変動(増減)が三ヶ月連続して前年同期比二パーセントを超えたときは、直ちに辞任する。 二 公共貨幣大臣が辞任した場合には、国会は二ヶ月以内に新規の公共貨幣大臣を承認・任命しなければならない。 三 公共貨幣大臣が不在の場合には、公共貨幣副大臣(供給担当)が代行する。 第四章 公共貨幣委員会 第九条 公共貨幣委員会は、公共貨幣大臣、副大臣二名を含む九名の委員から構成し、公共貨幣大臣が議長となる。委員の任期は公共貨幣大臣に準ずる。 二 議長は、委員会の会務を総理する。 三 議長に事故がある場合には、公共貨幣副大臣(供給担当)が議長の職務を代理する。 第十条 公共貨幣委員は、経済学、経営学、会計学その他関連する分野の博士号又はそれに相当する学識経験を有し、公共貨幣大臣および財務大臣がそれぞれ三名づつ推薦し、国会の承認を得る。 第十一条 公共貨幣委員会は、物価の安定を主任務としつつ、政府の経済政策と協調しながら完全雇用、持続可能な経済発展、及び公共の福祉の向上を達成することを任務とする。 二 この任務を達成するために必要となる公共貨幣の年間発行額の上限枠を設定し、国家予算の一環として、国会の承認を得なければならない。 三 さらに、年度内に於ける公共貨幣の需要と供給、及びその残高の管理等の調整を行う。需給の調整は、租税や政府支出に関する財政政策を通じて行う。 四 公共貨幣の年間発行額の上限枠の設定、および年度内に於ける需給等の調整はマクロ貨幣モデルを構築して行い、広く国民がシミュレーション検証できるようにする。 五 その他公共貨幣に関する全ての決定を行う。 第十二条 公共貨幣委員会の会議は、その任務達成のために議長が定期的に招集しなければならない。 二 議長が必要と認める場合又は委員の総数の三分の一以上が必要と認める場合には、議長は会議を招集しなければならない。 第十三条 公共貨幣委員会は、議長が出席し、かつ6名以上の委員が出席しなければ、会議を開き議決をすることが出来ない。 二 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決する。可否同数の時は、議長が決する。 三 議事の手続きその他委員会の運営に関し、必要な事項は委員会が定める。 四 委員会の議論及び議事録は全て公開とする。 第五章 公共貨幣管理運営委員会 第十四条 公共貨幣委員会は、公共貨幣管理運営委員会を公共貨幣省に設置し、日常の管理運営業務を代行させる。 第十五条 公共貨幣管理運営委員会の組織は、公共貨幣委員会が決定する。 二 公共貨幣大臣は、その委員を任命する。 第六章 公共貨幣庫第十六条 公共貨幣庫は、公共貨幣省に設置し、政府の銀行として国庫金を取扱い、また銀行その他の金融機関の間で行われる資金決済機関として機能する。 二 現行の日本銀行の施設(本店及び支店)は、そのまま公共貨幣庫に引き継ぎ、日本銀行の機能、業務のうち適性かつ効率的な運営に必要とするものを継承する。 三 機能・業務の必要性は、公共貨幣委員会が決定する。 第十七条 公共貨幣庫の管理運営は公共貨幣大臣が統括し、政府とは独立の公共貨幣庫財務諸表を作成して行う。 二 公共貨幣庫財務諸表には公共貨幣省の職員経費は含めず、職員経費は一般会計に計上する。 三 財務諸表は、会計監査院が監査する。 第七章 銀行預金の取扱い 第十八条 銀行預金は、取引のための預金(従来の普通預金及び当座預金等の要求払い預金からなり、以下、取引預金という)と投資のための預金(従来の定期預金等からなり、以下、投資預金という)とに大別する。 二 銀行は、取引預金を百パーセント準備金として公共貨幣庫に保管しなければならない。但し、取引預金のうち日々の取引に必要な現金は、現金資産として一部銀行で保管できる。 三 銀行は、取引預金に対して預金者に保管料を課金できる。 四 銀行は、準備金の不足分を保有国債で充当するか、または無利子で公共貨幣庫から借り入れることができる。 五 準備金に充当された国債は、その利息が保証され、満期日に額面額が償還される。 六 投資預金は信託された投資資金として銀行が貸し付けたり投資に運用することができ、その運用損益は投資預金者と共有できる。 第八章 公共貨幣制度への移行 第十九条 本法律施行日をもって、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律、及び、日本銀行法を廃案とする。 第二十条 本法律施行日から三ヶ月以内に、日本銀行を解散し、必要とする設備は公共貨幣庫に引き継ぐ。 第二十一条 日本銀行の職員はそのまま公共貨幣省職員とし、その扱いは国家公務員法に準ずる。 第二十二条 本法律施行日から三ヶ月以内に、日本銀行券を公共貨幣(紙幣)に交換し、その交換比率を一対一.一とする。 二 現行の政府貨幣は、そのまま公共貨幣(硬貨)として流通する。 第二十三条 本法律施行日から三ヶ月以内に、銀行の預金通貨口座はすべて公共貨幣預金口座(取引預金・投資預金)に変換する。 第二十四条 本法律に制定されていない移行にともなう管理・運営に関する決定は公共貨幣管理運営委員会が行う。